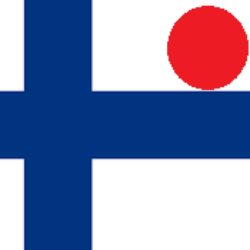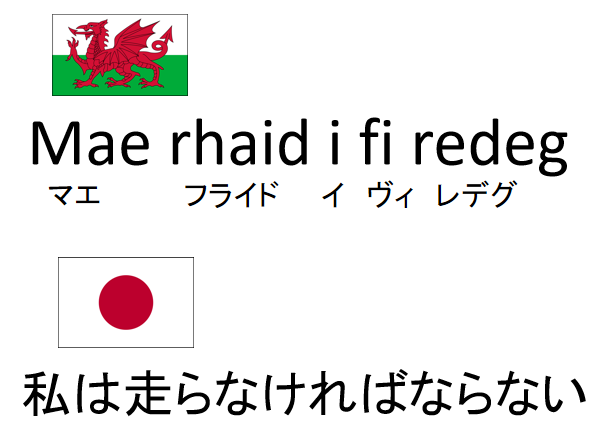「~があります」の構文を使って、
「~しなければならない」という義務も表せる。
前回の続き
例文
~する必要性が存在する
Mae rhaid i fi redeg
マエ フライド イ ヴィ レデグ
私は走らなければならない
直訳すると
私にとって、走る必要性が存在する。
Mae(マエ)=~がある
元々は「彼は~です」の意味。
だけど、今回の構文だと「~がある」の意味になる。
rhaid(フライド)=必要性
先ほどの「~がある」の対象が「必要性」
なお、rhaid(フライド)は名詞の模様
i(イ)=~にとって
i(イ)は代名詞「私」の意味もあるのだが・・・
ここでは、前置詞としての「i(イ)」
英語だと「to」のような感じ。
fi(ヴィ)=私
元々、「私」を意味する代名詞は「i(イ)」
それだと、前置詞+代名詞で
i i (イ イ)
になって読みにくい・・・・
だから、代名詞「i(私)」の形を
「fi(ヴィ)」
へと変えている。
まぁ、ほかの構文では
「i」が2つ並ぶケースもあるんだけどね。
redeg(レデグ)=走る
元の動詞の形は「rhedeg(フレデグ)」
だけど、「mae rhaid i+人」の後に動詞が来ると・・・
動詞の語頭の形が変わることがある。
rhedeg(フレデグ)→redeg(レデグ)
語頭が
rh→r
に変わってしまう。
こういう音の変化を軟音化(なんおんか)と呼ぶ。
軟音化(なんおんか)の紹介
ここまで、何度も「軟音化」というキーワードが出てきた。
なので、簡単に紹介しようと思う。
そもそも「軟音」って何?
軟音(なんおん)を簡単に説明すると・・・
「カクコ」に対して「キャキュキョ」と発音する時の舌の動き。
更に詳しく説明しようとすると「音声言語学」の知識が必要になる。
「軟音(なんおん)」を専門的に定義したのが
「口蓋化音(こうがいか)」だと思ってくれ。
私は「音声言語学」の事は全然知らないので
これ以上詳しく説明できない。
許してクレメンス。
ウェールズ語における「軟音化」
「軟音化」のパターンをざ~っと挙げると以下になる。
rh→r
p→b
t→d
c→g
b→f
d→dd
g→なし
m→f
ll→l
「軟音化」の例:「rh→r」
先ほど紹介した「走る」の意味を持つ動詞
「rhedeg(フレデグ)」だと・・・
rhedeg(フレデグ)→redeg(レデグ)
のように音が変わる。
これを、ウェールズ語文法では「軟音化」と定義している。
その他にも8パターンの音変化パターンがあるんですよ、
っていう話でした。
他の音変化パターンについては、
ず~っと先の記事で説明する予定。
まとめ
復習の意味で、3行にまとめてみた。
・義務は「~する必要性が存在する」で表現する
・「~にとって」を意味する前置詞「i(イ)」を使う
・「mae rhaid i+人」の後に来た動詞は軟音化(なんおんか)する
ウェールズ語講座その20へ続く